歯科矯正の支払いと医療費控除〜賢く節税する方法
歯科矯正と医療費控除の基本知識
歯科矯正を検討する際、多くの方が気になるのが費用の問題です。矯正治療は保険適用外となるケースが多く、数十万円から百万円近くかかることもあります。
しかし、ご存知でしょうか?歯科矯正の費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になるのです。
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が還付される制度です。これを活用することで、矯正治療の実質的な負担を軽減できる可能性があります。

歯科矯正が医療費控除の対象となる条件
歯科矯正の費用が医療費控除の対象になるかどうかは、治療の目的によって大きく異なります。国税庁の基準によれば、審美目的ではなく医療目的であることが重要なポイントです。
子どもの矯正治療の場合
子どもの歯列矯正は、医療費控除の対象になりやすいケースが多いです。特に発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象として認められています。
例えば、歯並びの悪さが顎や歯の正常な成長を妨げている場合や、発音が不明瞭で改善が必要な場合などが該当します。
大人の矯正治療の場合
大人の歯列矯正については、単に見た目を美しくするための「審美目的」の治療は医療費控除の対象外となります。しかし、以下のような機能的な問題を改善するための矯正治療であれば、医療費控除の対象となる可能性が高いです。
- 重度な出っ歯で食べ物を噛み切れない
- 受け口や開咬などで発音が不明瞭
- 噛み合わせの問題で顎関節症を引き起こしている
当院では、「なるべく歯を抜かない矯正治療」を推奨しています。矯正システム「MEAW(Multiloop Edgewise Arch Wire)」を採用し、従来の矯正治療で一般的だった抜歯を極力避ける方針を取っています。
医療費控除の対象となる費用と計算方法
歯科矯正において医療費控除の対象となる費用は多岐にわたります。治療に直接関わるものだけでなく、付随する様々な費用も含めることができます。
医療費控除の対象となる費用
歯科矯正に関連して、以下の費用が医療費控除の対象となります。
- 診察代、検査代
- 矯正治療でのの調整料・処置料
- 治療に必要な医薬品の費用
- 通院のための交通費(公共交通機関利用の場合)
子どもの治療の場合、付き添い人の交通費も対象になります。ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外です。
医療費控除の対象とならない費用
一方で、以下のような費用は医療費控除の対象外となります。
- 美容目的の歯列矯正やホワイトニング
- 予防目的の歯石除去
- 自家用車での通院時のガソリン代・駐車場代
- デンタルローンや分割払いでかかった金利
- 診断書の費用
医療費控除を受ける際は、これらの対象外費用を含めないよう注意しましょう。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額は以下の計算式で求められます。
医療費控除額 = 支払った医療費の総額 – 保険金などで補填された金額 – 10万円
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等×5%」を差し引きます。
例えば、年間の矯正治療費が50万円で、保険金などの補填がなく、総所得金額が300万円の場合、医療費控除額は「50万円 – 0円 – 10万円 = 40万円」となります。
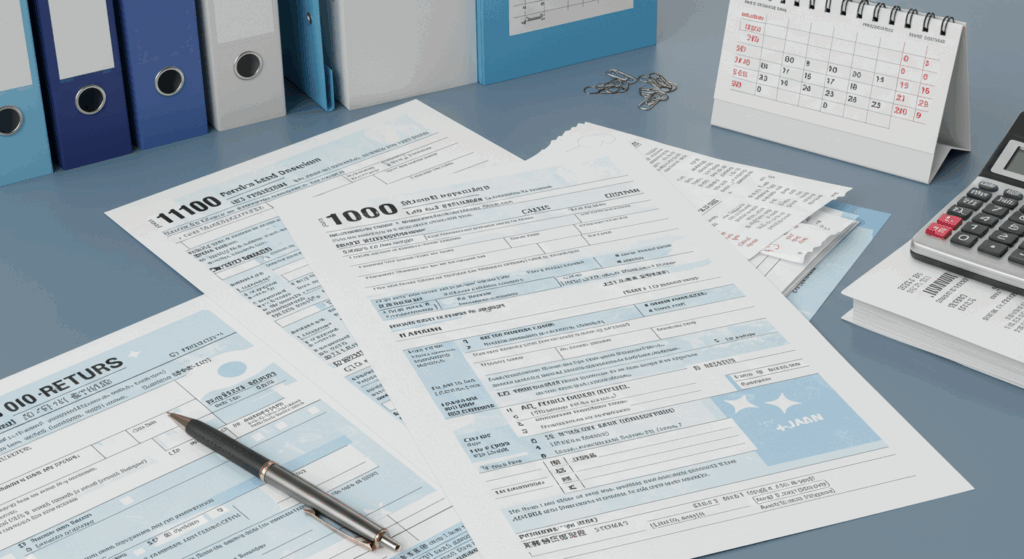
分割払いやデンタルローンを利用した場合の医療費控除
歯科矯正は高額になることが多いため、分割払いやデンタルローンを利用される方も少なくありません。この場合の医療費控除はどうなるのでしょうか?
デンタルローンの場合の医療費控除
歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立て替え払いし、その立て替え分を患者さまが分割で信販会社に返済していく仕組みです。
医療費控除の対象となるのは、信販会社が立て替え払いをした金額であり、その年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
実際に支払った年ではなく、契約した年が重要です。
注意点として、デンタルローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象外です。医療費控除を受ける際は、治療費本体の金額のみを申告するようにしましょう。
分割払いの場合の注意点
分割払いの場合も基本的には同様で、医療機関との契約が成立した時点での全額が、その年の医療費控除の対象となります。実際の支払いが翌年以降に渡っても、契約時の年にまとめて控除を受けることになります。
これは治療費の支払い方法が分割になっているだけで、医療サービス自体はすでに提供されたものとみなされるためです。
医療費控除の申請方法と必要書類
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。会社員の方も、医療費控除を受ける場合は自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告の期間と方法
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日までとなっています。
ただし、医療費控除は税金が戻ってくる「還付申告」にあたるため、1月1日から受付が開始され、さらに申告期間後でも5年以内であれば申告が可能です。
申告方法は、税務署に直接出向く方法のほか、e-Taxを利用したオンライン申告も可能です。
必要書類と準備
医療費控除の申告に必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票(会社員の場合)
- マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
- 銀行口座の情報(還付金の振込先)
2017年の税制改正により、医療費の領収書の提出は不要になりましたが、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。この明細書には、医療を受けた人、病院・薬局などの支払先、支払年月日、医療費の額などを記入します。
なお、領収書の提出は不要になりましたが、税務署から求められた場合に提示できるよう、5年間は保管しておく必要があります。
医療費控除で得られる節税効果
医療費控除を受けることで、実際にどれくらいの税金が戻ってくるのでしょうか?具体的な計算例を見てみましょう。
還付金額の計算方法
医療費控除によって戻ってくる税金(還付金)は、医療費控除額に所得税率をかけた金額です。さらに住民税も減額されます。
所得税の還付金 = 医療費控除額 × 所得税率
住民税の減税額 = 医療費控除額 × 10%
所得税率は所得によって異なり、5%〜45%の間で変動します。一般的な給与所得者の場合、多くは10%〜20%の税率が適用されます。
具体的な計算例
例えば、年収360万円の方が55万円の矯正治療を受けた場合、以下のように計算できます。
- 医療費控除額:55万円 – 10万円 = 45万円
- 所得税率:20%と仮定
- 所得税の還付金:45万円 × 20% = 9万円
- 住民税の減税額:45万円 × 10% = 4.5万円
- 合計の節税額:9万円 + 4.5万円 = 13.5万円
この例では、55万円の治療費に対して13.5万円の税金が戻ってくることになり、実質的な負担額は41.5万円に軽減されます。
医療費が10万円をわずかに超える程度の場合でも、所得税と住民税を合わせれば数千円から数万円の還付が受けられる可能性があります。特に高額な矯正治療の場合は、医療費控除を活用することで大きな節税効果が期待できるでしょう。

登戸クローバー歯科・矯正歯科の非抜歯矯正
当院の登戸クローバー歯科・矯正歯科では、患者さまの歯を極力残す「非抜歯矯正」を推奨しています。従来の矯正治療では、スペース確保のために健康な歯を抜くことが一般的でしたが、当院は矯正システム「MEAW(Multiloop Edgewise Arch Wire)」を採用し、なるべく歯を抜かない方針で治療を行っています。
非抜歯矯正のメリット
非抜歯矯正には、以下のようなメリットがあります。
- 健康な歯を残せる
- 顔のバランスが崩れにくい
- 治療期間が短縮できる可能性がある
- 抜歯に伴う痛みや不快感がない
特に子どもの矯正では、顎の成長を促すことで抜歯せずに治療できるケースが多いです。
当院の矯正治療の特徴
当院では、小児矯正の床矯正装置やワイヤー矯正だけでなく、マウスピース矯正も提供しており、子どもから大人まで幅広い年齢層の矯正ニーズに対応しています。
また、高性能のデンタルCT撮影装置を導入し、より精密な診断に基づいた矯正治療を提供しています。これにより、歯の位置だけでなく、顎の骨格や歯の根の状態まで詳細に把握し、より効果的な治療計画を立てることが可能です。
当院は、JR南武線・小田急線「登戸駅」から徒歩2分と通いやすい立地にあり、土曜・日曜も診療しているため、平日忙しい方でも通院しやすい環境を整えています。2025年6月には東京ヴェルディのグリーンパートナーにもなり、地域との連携も積極的に行っています。
まとめ:歯科矯正と医療費控除を賢く活用するポイント
歯科矯正は決して安い治療ではありませんが、医療費控除を活用することで、実質的な負担を軽減することができます。最後に、歯科矯正と医療費控除を賢く活用するポイントをまとめます。
- 歯科矯正が医療費控除の対象となるのは、審美目的ではなく医療目的の場合
- 子どもの矯正は医療費控除の対象になりやすい
- 大人の矯正でも、機能的な問題を改善する目的であれば対象になる可能性がある
- 医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた場合に適用される
- デンタルローンを利用した場合は、契約した年の医療費控除の対象となる
- 医療費控除の申請には確定申告が必要
- 領収書は提出不要だが、5年間は保管しておく
- 高額な矯正治療ほど、医療費控除による節税効果は大きくなる
当院の登戸クローバー歯科・矯正歯科では、なるべく歯を抜かない矯正治療を推奨しています。矯正治療をお考えの方は、治療内容だけでなく、医療費控除の活用も含めた総合的な視点でご検討ください。
矯正治療や医療費控除についてご不明な点があれば、お気軽に当院までご相談ください。患者さま一人ひとりに合った最適な治療プランをご提案いたします。
監修者情報
鈴木 聡(すずき さとし)先生
医療法人社団 緑幸会 登戸クローバー歯科・矯正歯科 理事長

略歴
広島大学歯学部卒業後、複数の歯科医院で研鑽を積み、幅広い症例に対応。現在は神奈川県川崎市にある「登戸クローバー歯科・矯正歯科」の院長を務めるとともに、登戸・東京都世田谷区桜新町に分院を展開しており、統括する医療法人社団 緑幸会の理事長として、地域の歯科医療に貢献している。
専門分野
矯正歯科・インプラント治療・審美歯科
特に、抜歯に頼らない「非抜歯矯正」や、目立ちにくい「マウスピース矯正(インビザライン)」に注力し、見た目と機能の両立を図る治療に力を入れている。
所属学会等
- 日本矯正歯科学会 会員
- 日本口腔インプラント学会 会員
監修者からのひとこと
患者さまの「見た目」と「噛める機能」の両立を大切にし、年齢やライフスタイルに合わせた矯正治療を心がけています。大人の方でも安心して始められる治療法をご提案いたします。




